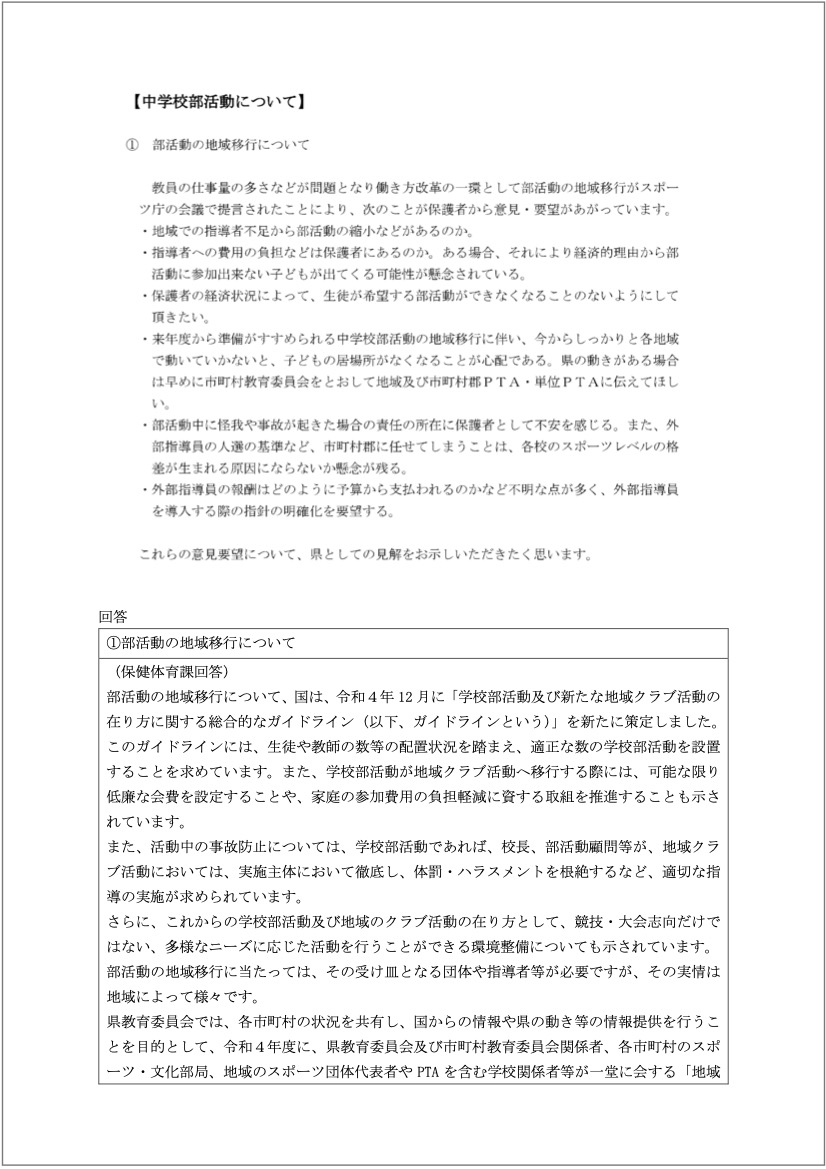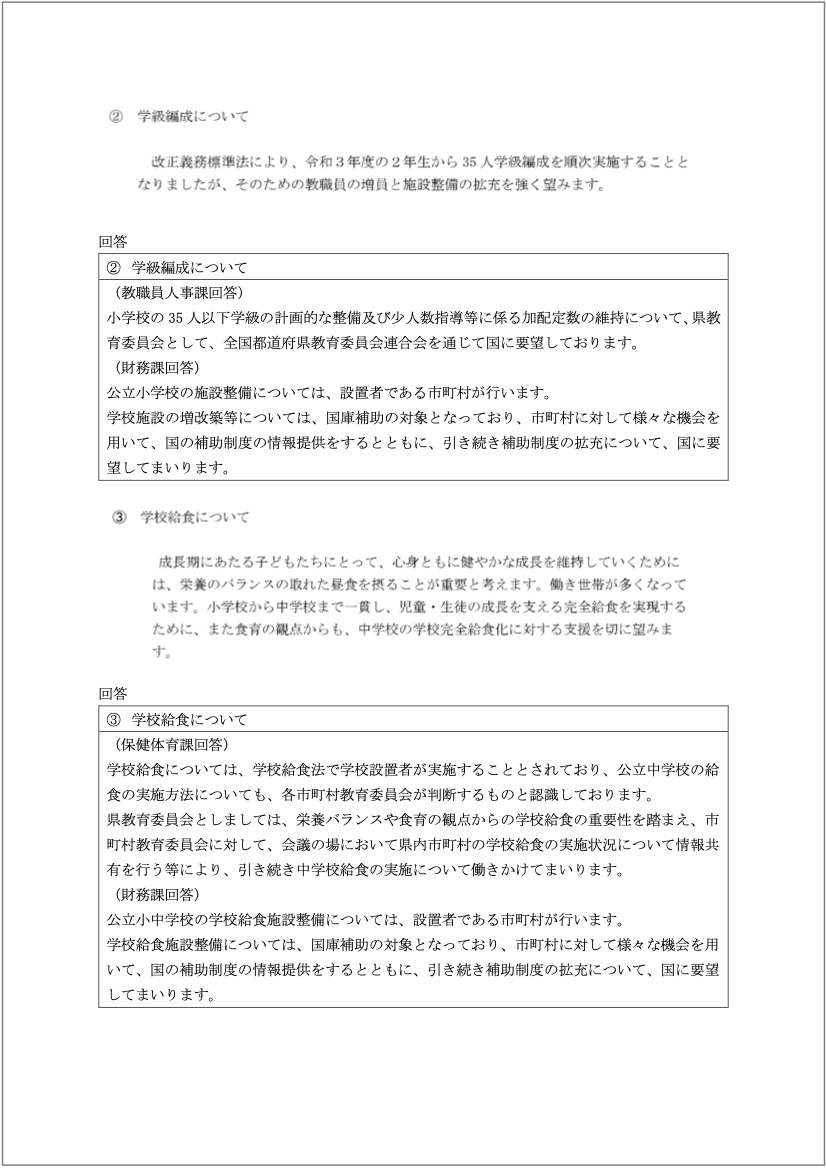県教育行政への意見・要望
令和6年度
1. 教員増員・改善
スクール・ サポート・スタッフが導入され、教職員の事務作業は減ったものの、まだ学校では人手が足りず、教員が授業以外で、もっと子どもたちと関われる時間を確保していただきたいと思います。また、教員の最も重要な業務である授業に向けた教材研究に充てる時間を十分に確保できない状況にあると感じております。
県教委より、教員の働き方改革についての状況を共有いただき、特に労働時間の改善については数字に表われており改善傾向にあると考えますが、教員の資質向上や教育の質の確保のために、教員の待遇改善や配置人数の加配等への対応を強く要望します。児童専任担当、教科担当制など新しい視点で、子供たちに取り組んでいる制度はとても賛同できるのですが、その対応に対しての人員増加があまり見込まれていないように感じます。その結果、教職員がさらに忙しくなっていることは無いでしょうか。各担当の負担が軽減できるように、人員増加をお願いいたします。
<回答>
児童指導担当・生徒指導担当については、国の定数改善計画を活用して配置基準を引き下げてまいりました。
教科担任制については、教科担任制の推進として国において令和4年度から教職員定数の改善がなされております。
各学校においては、配置された教職員定数をもとにして、業務内容を決定していると承知しております。
いずれの加配についても、全校配置を行うには県単独事業による教員の増員が必要であるため、本県の限られた財源の中では難しいのが実情です。県教育委員会としては、教員の組織的な指導力・対応力の向上を図るために十分な加配措置を行うよう国へ要望しております。
教員の待遇の改善については、県自ら国に要望しているほか、全国都道府県教育委員会連合会を通しても要望しており、今後も様々な機会をとらえて国に要望してまいります。
【昨年度回答に対する継続質問】
教員の待遇改善について
〇教員の資質向上について
教員の資質向上については、平成 29 年度に策定した「校長及び教員の資質向上に関する指標(令和 5 年度改定)」を踏まえ、引き続き、養護教諭、栄養教諭等を含むすべての教員を対象に、研修等による資質向上を図ってまいります。
⇒(継続質問)令和5年度改定の改定理由、狙いなどをご説明いただきたいです。
<回答>
県では、教育公務員特例法に基づき、国が定める「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」を踏まえて「校長及び教員の資質向上に関する指標」を策定しています。
令和4年8月の国の指針改定において、教員に共通的に求められる資質能力に、特別な配慮や支援を必要とする子供への対応及びICTや情報・教育データの利活用が追加されたことを受け、県においても令和5年1月に指標を改定しました。
教員の資質向上については、指標を踏まえ、引き続き、養護教諭、栄養教諭等を含むすべての教員を対象に、研修等による資質向上を図ってまいります。
〇教員の配置人数の加配について
教職員の加配については、標準法を踏まえ、各学校の実態に応じた配置を行っております。 今後も、各学校の実情を踏まえ、可能な限りの人的措置を行ってまいりたいと考えております。
⇒(継続質問)各学校の実情を踏まえるとありますが、どのように実情を把握されているのか、いつ、どのような方法で実情を確認するのかを教えていただきたいです。
<回答>
次年度の定数を配当する際に、学校を管理・監督している市町村教育委員会から要望等を受け付けています。
〇基本給の見直しについて
優秀な人材確保の観点から、教員の初任給については、一般行政職員に比べて優遇措置を とっており、令和5年度の給与改定においても、初任給や若年層が多く在職する級号給の給料表の引上げを行っています。
⇒(継続質問)新卒採用の給料が上がる中、現役職員の残業手当が少ないように感じます。
中核を担う職員の給与体制の見直しや改善をなどは考慮されているのか 確認させていただきたいです。
<回答>
教員については、修学旅行等の学校外での教育活動や、学校外の自己研修など、その職務と勤務態様の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額が支給されています。
国は、中央教育審議会の答申を踏まえて、令和12年度までに段階的に教職調整額を10パーセントに引き上げることとしたほか、学級担任への⼿当の加算や若⼿教師のサポート等を担う新たな職の創設など、職責や業務負担に応じた給与体系とすることを検討しており、その動向を注視してまいります。
〇教員の業務をサポートする体制の充実化について
教員がより児童・生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備するため、児 童・生徒の指導に関わる業務の一部等を担い、教員の業務をサポートするスクール・ サポート・スタッフを令和2年度から配置しています。 働き方改革の推進において、スクール・サポート・スタッフの果たす役割は大変重要 と考えていることから、令和6年度においても、国の補助事業を活用し、政令市を除く市町村立小・中学校等にスクール・サポート・スタッフを全校配置する措置を講ずることといたしました。 今後も引き続き、スクール・サポート・スタッフの配置規模拡充と全校配置につい て、国に要望してまいります。
⇒(継続質問)スクール・サポート・スタッフの配置状況について、R6の状況と、R7の 予定を可能な範囲で教えていただきたいです。
<回答>
令和6年度については、政令市を除く市町村立小中学校等に全校配置済みとなっております。令和7年度も引き続き全校配置する措置を講ずることといたしました。
2. 教員の働き方改革
■教職員の働き方改革にも貢献できるような推進について
新聞、ニュース等では、教職員の賃上げについて報道されていましたが、教職員の長時間労働や 負担を軽減すること、教職員が安心して働くことができる環境を整えることが重要と思います。
教職員の労働環境が改善され負担が軽減した分、担任の先生が子どもたちと向き合う時間 (例えば、子どもたちにとっての魅力的な授業・教材研究やいじめ問題等)がしっかりと確保できるようになると考えるからです。
労働環境に対する懸念を主な要因として教員志望者が減少していると同時に離職者や休職者が増加しており、教育の質が著しく低下する恐れがあると危惧しています。
働き方改革が提唱されて、様々な改革から徐々に負担も軽減傾向にはありますが、未来を担う子どもたちへの質の高い教育を確保するため、また教職員が【学校教育の要】である“子どもたちに寄り添いながらその成長を実感することのできる”本来のやりがいへとつながるためにも、より一層の働き方改革の推進をお願いしたいと思います。
県としては、教員の働き方改革の促進化に向けて、様々な方策をお考えのことと思います。 あらためて下記2点について、県としての今後の方針やお考えをお示しいただきたく思います。
〇人づくりの観点から、これから教員を目指す人(学生・社会人を含む)に対して、教員の魅力と やりがいをどのように発信し、どのように増やしていこうとしているのか、教育の担い手を確保 するためのお考えがございましたらお聞かせください。
<回答>
人材の確保に当たっては、まず、採用試験における工夫・改善として、一定の社会人経験のある方に対して、一次試験の一部を免除する特別選考の資格要件の緩和や、これから教員免許を取得する人の教員採用試験受験を可能にし、最大2年間の採用延期を認める選考を実施するなどの取組を行っています。
さらに、小学校を対象として、これまでの夏期試験に加え、令和6年度から新たに秋期試験を実施しています。
また、大学生等に対する働きかけとして、全国の大学等に直接出向いて説明会を開催し、教職課程を履修している学生に対して、教員の魅力や本県の働き方改革の取組を説明して、本県の採用試験受験の働きかけを行っています。
今後も様々な取組を行い、可能な限り教員不足の解消を図っていきます。
一方、代替教員の確保に当たっては、臨時的任用職員及び非常勤講師の登録について、県のたよりにお知らせ記事を掲載することや、教員採用試験の際にお知らせの文書を配付するなど、制度周知に取り組むとともに、更なる人材の確保を図るため、教員免許を所有する社会人や教育現場を長く離れている方などを対象に、教員を志願するきっかけとしてもらうことを目的とした「ペーパーティーチャー研修」を実施し、この研修の中で臨時的任用職員等の登録受付を行うなど、必要な人材を確保できるよう努めています。
なお、教員の人材確保については、国にも対策を講じるよう、県の重点的提案として働きかけを行うとともに、全国都道府県教育委員会連合会を通じて要望しています。
〇教員以外に子どもたちと直接関われる人材(例えば、定年退職した教職員や民間企業と連携しての外部人材を登用・活用)を増やすことにより、教員不足の解決や教職員の労働環境改善に 対して一定の効果があるのではないかと考えます。また、教職員以外のより多くの人と関わることにより、子どもたちの今後の人生を豊かにすることにつながるのではないかとも考えます。それらの登用・活用についてお聞かせください。
<回答>
県教育委員会では、令和5年度から、政令市を除く公立学校において心理の専門職であるスクールカウンセラー等の配置を大幅に拡充し、政令市・中核市を除く公立学校において社会福祉の専門職であるスクールソーシャルワーカー等の配置を大幅に拡充するとともに、困難を抱える子どもたちをプッシュ型(積極的)面談等により早期に把握し、医療や福祉等のアウトリーチにつなげていく仕組みである「かながわ子どもサポートドック」に取り組み、各学校の教育相談体制の充実を図っています。
また、教職等の子どもに係る課程を履修中の大学生等のボランティアが、教員とは異なる立場で子どもたちにかかわる「スクールライフサポーター事業」を実施しています。
3.部活動地域移行
■部活動地域移行の推進に係る、教員の働き方改革について
部活動の地域移行については、県として方針を示し、地域の実情に応じて、市町村が判断して進めていくものであると認識しています。しかしながら、その進展は、地域により大きな差が生じていると感じております。教員の働き方改革も考慮して、部活動の地域移行が進められておりますが、取り組んでいる地域のスポーツ・文化芸術活動関係者のほとんどが、部活動の地域移行は教員の働き方改革に関係していることをあまり認識していないように感じられます。
スポーツ庁 室伏 広治長官が 「子供たちがスポーツ・文化芸術活動に継続的に親しめる環境づくり」 が重要であるとコメントされておりましたが、スポーツ・文化芸術活動関係者には、部活動の地域移行は働き方改革に寄与することであるということを理解し推進していただきたいです。
<回答>
令和5年10月に「公立中学校における部活動の地域移行に係る神奈川県の方針」を策定しました。本方針の基本的な考え方の持続可能な活動環境整備において、休日の部活動指導に係る教員の負担軽減を目指すことが記載されております。今後も地域移行連絡会や会議等、様々な機会をとらえて、情報発信をしていきます。
4. ICT
■ICTの活用及び情報モラル教育、ネットリテラシー教育の充実について
コロナ禍で進んだ ICT 活用ですが、今後も積極的な活用を進めて欲しいと思います。タブレットを使った授業や、オンライン授業、今後デジタル教科書の導入、メタバース環境など学校がICTを活用していく場面は益々増えていき、それに伴う情報モラル教育、VDT症候群(デジタル健康被害)などを考えると、教員が勉強して使うというレベルを超えている(教員の多忙化も促進している) 教職員の準備や努力などが必然とされている状況であると考えます。ICTを最大限に活用し、豊かな教育活動を行うためにも、ICTの専門職が各学校に常駐するように配置をご検討ください。
情報支援員などによる情報モラル教育の充実及び深刻なケーススタディの情報共有により、未然のトラブルを回避できる環境整備の強化についてご検討ください。
ネットを介したいじめに関する道徳科の授業の具体例を掲載した指導資料を作成、配布いただき、ネットモラル教育の一層の推進をお願いいたします。
昨今は、闇バイトなどの犯罪に巻き込まれるケースが増えている為、一早い対応が必要と考えておりますので対策の検討を強く要望します。
<回答>
限られた財源の中、県独自でICT支援員を配置することは困難ですが、希望する学校全てにICT支援員を配置できるよう財政措置の更なる充実を図ることを、全国都道府県教育委員会連合会等を通じて要望しており、引き続き国に対して、要望していきます。
昨年度、ネットを介したいじめに関する道徳科の授業の具体例を掲載した指導資料を作成し、県内の児童・生徒指導担当教員が参加する会議等で周知し、活用を促しました。今後も引き続き、会議等において指導資料の積極的な活用を促し、ネットモラル教育の一層の推進を図っていきます。
また、児童・生徒が自他の権利を尊重し、情報社会での行動に責任をもつとともに、犯罪被害を含む危機を回避し、情報を正しく安全に利用できるようにするために、「ICT を活用した学びづくりのための手引き(小・中学校)」を順次更新し、各教科における情報モラル教育を推進していきます。
5. 支援・サポート
■小中を見通したサポート体制の確立
現在の小学校では、通級指導教室が設置され、児童のサポートが行われておりますが、中学校には通級指導教室の設置が無いため、入学後に困り感をもつ生徒がいると考えらます。また、小中共通で不登校生徒が学べる放課後の施設は少ないのも現状です。(地域の方々の厚意でいくつかの教室が開室されているが、受け入れには限界がある)
さらに、神奈川県立の高等学校にはインクルーシブ教育実践校が設置されており、現在18校と増えてはいるものの、移住地により選択が難しい場合が考えられます。
これらのことから、小中高とそれぞれがサポートする独立した現在の体制を見直し、途切れることの無い子供の将来を見通した支援体制の確立を要望します。
<回答>
県教育委員会では、さまざまな課題を抱えた児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応していくことを学校教育の根幹に据えた支援教育を推進しています。
公立小・中学校において、すべての児童・生徒が自立と社会参加に向け、個々の特性や能力に応じた教育を受けられるよう、県教育委員会では、支援が必要な子ども一人ひとりに、成長の過程をたどるライフステージに沿った支援(タテのつながり軸)と、教育、保健、医療、福祉、労働等の諸機関の連携(ヨコのつながり軸)による支援というタテ・ヨコの2つの軸で整理した、「支援シート」を連携のツールとして導入しています。
今後も、市町村教育委員会と連携し、就学前から卒業後にわたり、切れ目ない子どもの学びと成長をつなぐために「支援シート」を活用し、関係機関と連携した円滑な情報の共有、引継ぎを推進していきます。
■支援体制の充実について
子どもたちの抱えている問題が多様化しています。外国につながりのある子ども、保護者も増えてきています。英語以外の言語を母国語としている為、共通言語が無いことが増えているようです。また、思春期と特性により、中学生になると、小学生とは違う対策が必要になってきます。これらのことに対応できるように、多言語にわたる日本語指導協力者を配置する支援の充実をお願いいたします。
]
<回答>
日本語学習の支援や通訳派遣に係る支援について、外国につながりのある児童・生徒の支援体制を整備するため、国庫補助を活用して「帰国・外国人児童生徒等教育推進支援事業費補助」として、市町村が公立小・中学校に日本語の指導・教科学習の補習を行う支援員を配置するために要する経費などを補助しており、国庫補助率の拡大について、全国都道府県教育委員会連合会を通じて国に対して引き続き要望していきます。
6. 不登校・いじめ
■いじめ問題について
「こどものこころに寄り添う」と言われてはおりますが、そのためには教職員の心と時間のゆとりが必要であると感じております。 また、いじめの未然防止、早期発見、早期対応など、学校側もさまざま措置を講じてはいるものの、発生してしまったいじめ事案について、いじめを受けた児童へのケア・その保護者側の支援は言うまでもなく、いじめの加害者に対しての指導は、加害者側の保護者を交える等、学校と家庭が連携し、毅然とした姿勢での徹底した指導をお願いいたします。教職員とスクールカウンセラー等が連携したスクリーニングや、プッシュ型面談等により、チーム学校として、いじめの早期発見、早期対応をお願いしたいです。その際、いじめ問題を担当している教職員の心のケアについても併せてお願いいたします。
<回答>
学校は、いじめを行った児童・生徒に対しては、「いじめは決して許されない行為である」ことを、適切かつ毅然と指導するとともに、当該児童・生徒の成長への支援という視点に立って、いじめの行為に至った背景等を丁寧に把握し、寄り添いながら対応しています。
また、ケースによっては、いじめを受けた児童・生徒の立場に立って、「いじめ」という言葉を使わずに指導することもあります。いじめを受けた児童・生徒に対しては、最後まで守り通すという認識のもと、すぐに安全を確保するとともに、当該児童・生徒に寄り添い、心のケアを行うなど、家庭と連携して支援しています。なお、いじめが解消している状態と判断した場合でも、関係する児童・生徒の状況を、日常的な関わりの中できめ細かく把握し、いじめの再発防止に取り組んでいます。
また、いじめを受けた子どもやいじめを行った子どもが立ち直っていくためには、医療や福祉などの専門機関と協力して、指導・支援する必要があります。また、犯罪につながるおそれのあるいじめについては、警察と連携して対処する必要があります。
県教育委員会では、保護者や地域の皆様に、いじめ防止への理解をより深めて頂けるよう、「いじめ防止啓発リーフレット」を作成し、ホームページで掲載しています。
また、令和5年度より「かながわ子どもサポートドック」の取組を推進しており、教員とスクールカウンセラー等が連携したスクリーニングや、プッシュ型面談等により、チーム学校として、いじめの早期発見、早期対応を行っています。
さらに、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むにあたって中核となる学校いじめ対策組織が的確に情報を共有し、その情報をもとに教員が抱え込まずに組織的に対応できるような体制とすることを、市町村教育委員会と連携して、各学校に働きかけていきます。
県教育委員会としては、引き続き、家庭や地域社会、関係機関等と連携しながら、各学校におけるいじめ対策の推進を図っていきます。
7. スクールカウンセラー
■スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーの学校常駐化あるいは勤務日の増加について
子供を取り巻く様々な環境が多様化している中、より細やかなサポートが必要になっております。スクールカウンセラーやソーシャルワーカーへの相談件数が増加している一方で、来校日は週1~2回、月3~4回程度のため、予約が取り難いのが現状です。スクールカウンセラーの来校回数が少ないと保護者は会う機会も少なく、面談を申し込むこと自体に大きな壁を感じてしまいます。
スクールカウンセラーの増員は保護者だけでなく、子供たちの安心感につながると考えております。「いつでも先生に相談して良いよ」と言われても、クラス担任はいつもだれかと話しをして、忙しくしており、保健室の先生も誰かが出入りしているので話し出せるきっかけが難しく、悩みやすい子ほど、まわりに気を使って相談するタイミングがつかめないでいるように感じております。
カウンセラーが普段から学校に常駐していれば、児童の様子も見ることができ、児童も初めて会う人に相談するのではなく、「知っている人」だとだいぶ違うと思います。
放課後についても、継続して開いていれば、日中の出来事でも相談ができ、仕事をしている親も利用しやすいのではないかと感じております。ぜひご検討ください。
<回答>
スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化等について、全国都道府県教育委員会連合会等を通じて要望しており、引き続き国に対して要望していきます。
8. インクルーシブ教育
■インクルーシブ教育を進める上で、教育委員会と福祉課の連携を期待
障がい福祉課の在り方検討会への教職員の参加など、学校に在籍している個別の対応が必要な生徒については、自立を目指し、障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服しようとする取り組みが行われております。障害の重度・重複化、多様化に対応し、適切かつ効果的な指導を進めるためには、専門的な立場(例えば理学療法士、作業療法士等)の方との連携が必要となりますが、連携が十分に行われているとは言えない状況であると感じております。
学校と専門的な立場の方との連携が地域差等なく、よりスムーズに行えるような環境を整えていただきたいです。 そのためにも、組織間での連携がしっかりと行えるような体制強化を要望 します。
<回答>
本県では、共生社会の実現に向け、すべての子どもが、同じ場で、共に学び共に育つことをめざし、インクルーシブ教育の推進を進めています。
すべての子どもが、集団の中で互いを理解しながら社会性・思いやりの心を育むためには、子ども一人ひとりに多くの教職員が関わり、多面的に子どもの状況を把握した上で、本人を中心に、保護者や教職員、様々な職種の関係者による対話を通して教育活動へ参加できる手立てや環境づくりを検討していくことが重要です。こうした体制づくりを推進するため、県教育委員会は、障がいのある子どもや医療的ケアが必要な子どもを支援するために福祉子どもみらい局が中心となって設置している会議に出席するなど、全庁的な連携を図っていきます。
9. 自然災害
■大規模地震、大雨、災害時の対応について
避難訓練や防災教育の充実を目的とした講習や地域との連携の大切さの啓発などは各学校、 自治体で実施しておりますが、地域によっては、土砂崩れなどで主要道路が通行できずに孤立する恐れが強いため、災害発生時からの数日間に及ぶ安全管理計画を検討、改定していただきたいです。
<回答>
災害発生時に児童・生徒等の安全を確保できるよう、県立学校全校で地域の特徴(土砂災害警戒区域・洪水や津波の浸水想定区域等)に応じた独自の「学校防災活動マニュアル」を作成しており、災害発生時からの教職員等の対応についても記載しています。
各学校は、毎年度、総務室が作成する指針や作成例に基づき、マニュアルの点検・更新を行っているところですが、より実態に即したものとして整備されるよう、総務室と学校で協力していきます。
なお、改訂した内容等については、毎年度各市町村教育委員会にも共有しておりますので、引き続き、ご活用いただけるよう取り組んでまいります。
10. 性教育
■性教育拡充について
2024年9月に茅ヶ崎で発生した性被害の記事について、「茅ヶ崎市立小学校」と記載されているため、茅ヶ崎小学校関係者には多くのクレームが寄せられております。(1時間以上の電話も多数)
記事の表記の問題だけでなく、再発を防ぐための対策として、児童への性教育の拡充をお願いいたします。SNSやYouTube等で低学年でも自由に映像が見られる時代であり、正しい知識を与えるために専門の方に指導してもらえると安心です。県では、「性に関する指導の手引き」を作成し教員の指導資料としていますが、これを積極的に活用し、教員だけでなく保護者を含めた性教育の理解を得る施策を行って欲しいと考えます。
<回答>
国は、性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議において、令和2年「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」、令和5年「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」を示しました。その方針を踏まえ、発達段階に応じた教育・啓発活動として「生命(いのち)の安全教育」が推進されています。県教育委員会においては、平成16年に作成した「性教育指導の手引き(教師用)」を令和4年3月に「性に関する指導の手引き」として改訂し、「生命(いのち)の安全教育」が各学校で適切に実施されるよう働きかけているところであり、「性に関する指導の手引き」には、保護者向け周知資料及び「生命(いのち)の安全教育」を実施する際の保護者への対応のポイントも掲載されております。
県教育委員会としては、引き続き現行の方針に従って、子ども達が生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を発達段階に応じて身に付けることを目指した「生命(いのち)の安全教育」を推進してまいります。
11. 教育予算増額について
■国・県の教育予算増額の拡充について
〇体育館空調設備のための「助成金等の処置」について
近年の温暖化に伴い、熱中症アラート発令時などは、熱中症予防のために空調設備がない体育館は使用できません。集会が実施できなかったり、学習活動に制限がかかったりするなどの影響が出ております。内閣府が、昨年7月に「避難所に指定されている施設に空調設備の設置」を呼びかけていることも鑑み、早期の設置を実現させるために、市町村への手厚い助成金などの措置をお願いいたします。
<回答>
体育館における空調設置については、国の令和6年度補正予算において、空調設備整備臨時特例交付金が創設され、避難所として活用される学校体育館等について、令和15年度まで補助率2分の1で整備が可能となっています。
県としましては、小中学校の設置者である市町村に対して、交付金の活用を周知すると共に、引き続き補助制度の拡充について国へ働きかけていきます。
なお、公立学校施設整備に係る役割分担上、県の補助制度を創設することは、考えていません。
〇学校施設の修繕費の拡充について
校舎の修繕費・エアコンの整備・水道管の取り換え等・トイレ洋式化、子供たちが生活する学校の施設整備が行われていない状況があるように思います。各市町村ではまかないきれない予算額になるため、国・県として、子供たちが安全に安心して学校に通うことができるように学校施設の修繕等のための補助金の拡充を要望します。
<回答>
公立学校施設整備に係る必要な財源の確保については、国に対して全国都道府県教育委員会連合会や全国施設主管課長協議会などを通じて要望しており、今後も継続して要望していきます。
また、県教育委員会自らも、施設整備事業に係る補助制度の拡充について国に対して要望をしており、今後も設置者の計画事業が円滑に実施できるよう国へ働きかけていきます。
12. トラブルに関しての情報提供依頼について
子どもに関するSNSなどの投稿やトラブルも増えております。残念ながらSNSを通じた誹謗中傷などのトラブルは後を絶たず、心を痛めている人が少なからずいるのが今の現実です。もしもそのような被害やトラブルに遭った時に、少しでも参考にしていただければと考え、神奈川県PTA協議会ホームページでも情報提供しておりますが、県教育行政側からもトラブルに関する啓発資料や、相談窓口があれば情報提供をお願いいたします。
<回答>
SNSを通じたトラブルに関しての情報提供を3点いたします。
①「PTA活動のためのハンドブック」
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gt2/ptahandbook.html)
保護者や教員向けに生涯学習課が作成しています。
この中には、「情報メディアの正しい活用法」、コラム「SNSによる性被害に遭わせないために」、「中高生SNS 相談@かながわ」について掲載しています。
②かながわ「いのちの授業」指導資料
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3p/cnt/f417796/index.html)
子ども教育支援課が作成しています。
いじめについて考えることを主とした資料ですが、いじめに気付くための組織的な取組に関すること、情報モラル教育の重要性、ネット上のいじめ等、SNSを介したインターネット上のトラブルについて啓発を行っています。
③神奈川県ホームページ「インターネットと人権」「人権について考えよう(若年層向けの人権啓発まとめサイト)」
福祉子どもみらい局共生推進本部室では、人権問題に関するホームページを公開しています。
〇「インターネットと人権」
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f480024/index.html)
このページでは、インターネットと人権侵害について発信しているほか、各種相談窓口を案内しています。県として、インターネット上の誹謗中傷専門相談を実施しています。
〇「人権について考えよう(若年層向けの人権啓発まとめサイト)」
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f480024/jinken_jakunen.html)
このページでは、中学生~高校生向けとして、インターネット・SNSに関する人権啓発の動画や教材を掲載しています。
以 上
神奈川県PTA協議会では、PTA活動に関するSNSなどの投稿やトラブルについて、情報提供をしています。↓
令和5年度






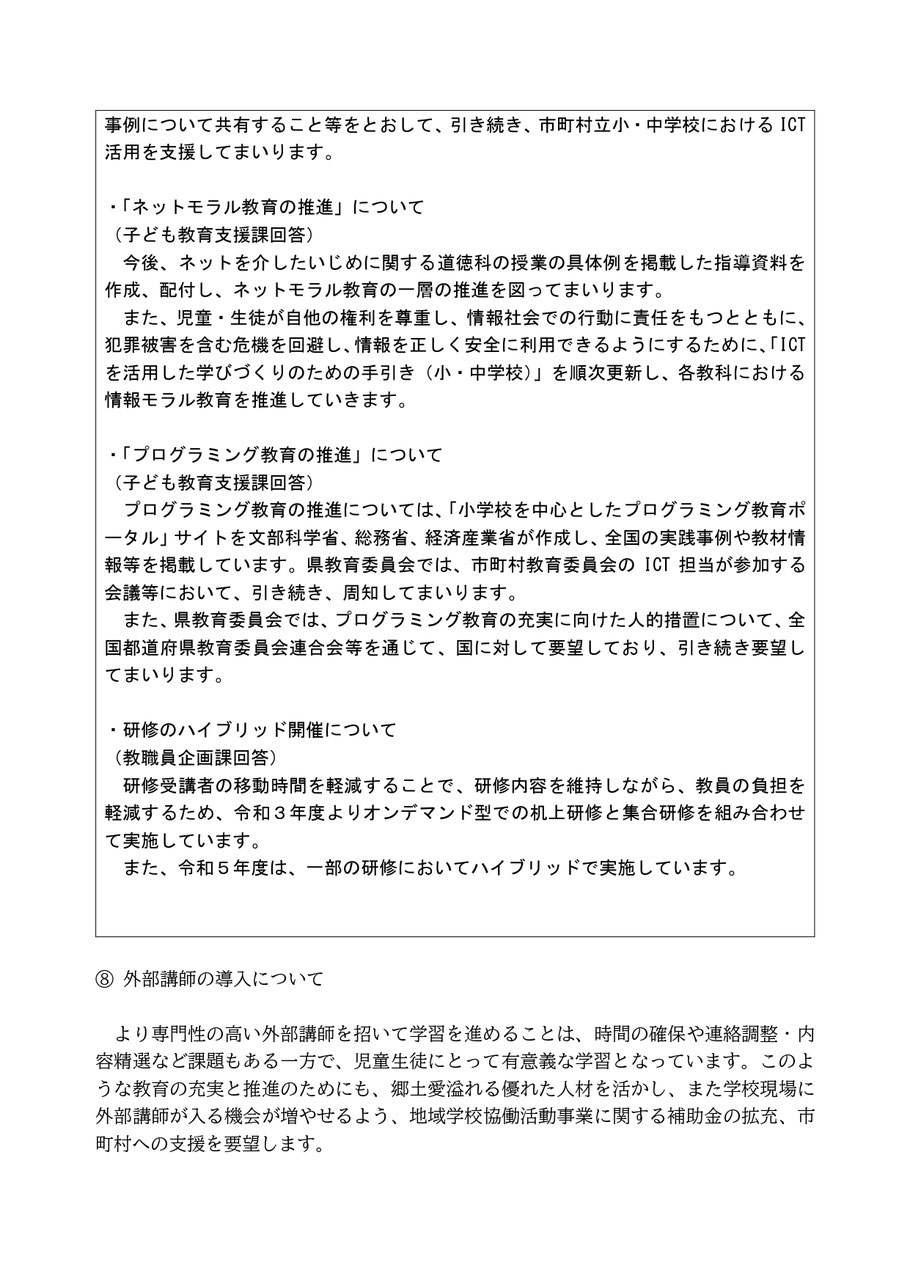


令和4年度
神奈川県教育委員会への意見・要望と、それに対する回答を掲載します。
【意見・要望内容】
① 不登校児童・生徒のケア及びサポートについて
② 中学校部活動について
③ 教職員・養護教諭の負担軽減について
④ 学校再編(学習格差、学級編成、専門家の授業、統廃合等)について
⑤ インクルーシブ教育について
⑥ ネットモラルについて